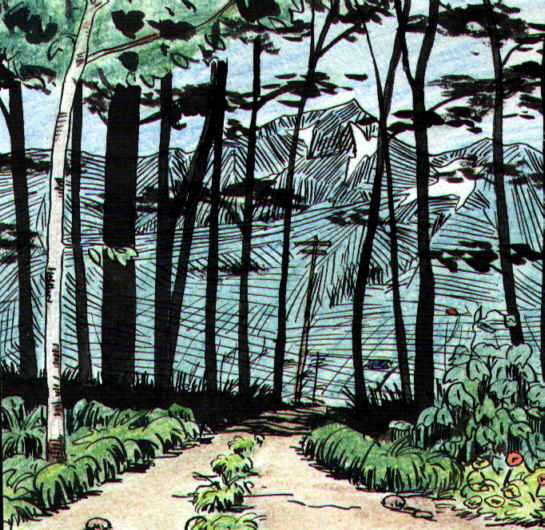(2021.11.04 up / 2025.02.23 update) Back Top
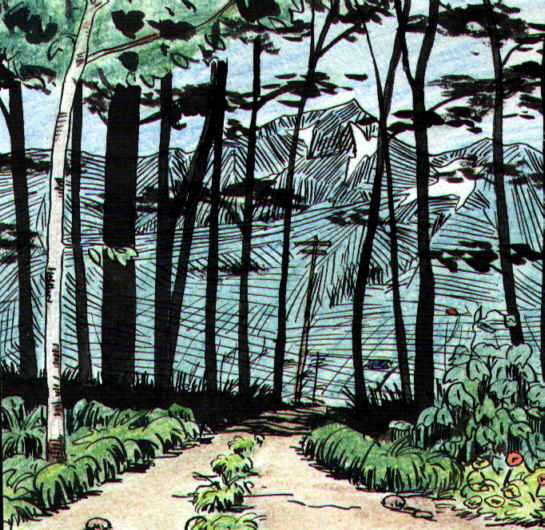
「四季・コギト・詩集ホームぺージ」について
とある文学サイト管理人の思い出
『詩と思想』 2021年10月号「地域からの発信 岐阜」への寄稿誌面 (新かな遣い)
1999年に文学サイト「四季・コギト・詩集ホームぺージ」を開設してからもう随分経ちます。当時はまだスマホもtwitterもヤフオクもありません。Windowsが次々とアップデートしてゆくなか、パソコンと共にインターネットが一般に普及していった時代でした。“誰でも手軽にホームページが作れる”ようになったのですが、界隈の様子はまだまだ牧歌的でした。“炎上”が社会的注目を浴びる現在とは無縁の気分のなかにあったことを、サイトに付設した掲示板の過去ログを久しぶりに開き、赤面しながら思い出しています。
コンテンツだけは年と共に増えてゆきます。が、文芸分野など訪問者も尠く、未だにページの作り方にも工夫や進歩がありません。そして何の保障もなければ、いつか管理人と共に跡形もなく消えてしまう、そんな運命も見え隠れする運営を続けています。
昨今は“忘れられる権利”なるものも云々されるようになりましたが、将来ネット情報の歴史をひもとく際に「地域からの発信」として、かつてこんな文芸サイトにまつわる逸話があったことを一度は紙上の記録として残して置いて良かろうと、この度の執筆依頼を有難くお引き受けしました。
1.「開設に至るきっかけ・詩との関り方」
私がこのホームページを作ろうと思ったのは、ありていに言えば、自分が現代詩に馴染むことができなかったからでした。今を生きる詩人として名を成すことを諦めたのが、お粗末ですが正直な理由です。
先輩方から「書き続けたほうがいいよ」とよく言われましたが、抒情的な詩観が決して主流になる事のない詩壇に拘泥するより、自分に感動を刻印した、愛する詩人たちに寄り添っていたかった。とりわけ戦後詩壇からは“花鳥諷詠”と軽んじられ“戦争詩”に手を染めたと罪人のように指弾され続けてきた、昭和戦前期にデビューした抒情詩人たち。彼らの詩的血脈の最後に自分を置いて、その業績を、紙媒体の同人誌に拘り続ける詩人たちよりも新しい、ネット世代の読書子に紹介して彼らからの賛同を俟つこと。
その方が同時代に同志を作れなかった自分の、詩人としての鬱屈を鎮めてくれる気がしたのです。
詩は我が強くなくては書けないし、書き続けてゆけません。エゴの強い私はエゴを持したまま、やりたいことが何か自分以外の役に立つことになるような“詩作に代わるもの”がないものか、考えた末に詩との関はり方を改めたのでした。
2.「開設に至るきっかけ・師と詩集と」
幸い私には、東京で詩を書いていた20代の頃、戦前の『四季』『コギト』の編集同人だった詩人、田中克己[1911-1992]の謦咳に接したという心の遺産がありました。口語抒情詩の美が最高水準を示した当時の四季派、日本浪曼派、そしてモダニズムにまたがる主要な詩人の人脈すべてに関り最も若かった詩人です。田中先生がご存命であることを聞き及んで、ある日突然、教え子でもないのに押しかけ、その門を最晩年に敲き得たことを、私は詩人として最高の、かけがえのない幸せに感じています。
謂わば詩史上の“遺民・遺臣”を自任して、故郷の岐阜に帰ってきた私は、亡くなった先生の顕彰を第一に、まずは遺された詩作日記と詩集を編集して形にすることに力を傾注しました。一方で他の、我が“知己”に勝手になぞらえられた詩人たちとの交歓のためには、直結する媒体として、彼らの初版本詩集を集めることに励みました。
在京時代から神田神保町の田村書店にせっせと通い、帰郷後は郵送を心待ちにした石神井書林や新村堂古書店、地元の鯨書房などからの古書目録を通じて収集が続けられました。詩文学ばかりで占められた蔵書は現在、3000冊余りになったでしょうか。
詩人の思いが込められた装釘や、造本に色濃く表れた時代の佇まいに囲まれ、自分もまた四季派の末輩として殉ずるのだ──そんな綺麗事など言わなくとも、コレクションの蒐集は、詩を書かなくなった好事家の詩生活(私生活)を、大いに物欲で慰めてくれました。薄給の身でありながら、あこがれの詩人たちの原本詩集を揃えたいなんて、冊子体の表現活動に拘っていたら考えられないことです。
さきに申し上げた“誰でも手軽にホームページが作れる”時代がやってきたのは、刊行成った田中先生の本を、今度は電子化してネット上に公開したい、同時に、忘れられつつある当時の抒情詩人もピックアップして、紹介かたがた蔵書自慢をしたくなった、そんな時のことでした。
3.「ホームページ開設」
1999年、サイトが無事開設できたのは、実際には私が職場の大学図書館に異動となり、サーバーの空き領域を無断で使用できたからです。
それまで方々に書き散らしてきた拙文【四季派の外縁を散歩する】を付して、先生の日記と著作目録とを主な内容とする【田中克己文学館】を主要コンテンツに掲げ、upしてみました。始めてみたところ、内からも外からも反応なく、また咎め立てもされません。そんな鷹揚な環境のもとに出発した、もぐりの個人ホームページでした。
現在は、後で紹介するサイト管理人の御厚意に与り、サーバーを移して有難く居候させていただいていますが、情報を管理する上でのいい加減さということでは、戦前の稀覯詩集を紹介する際、“書影”こそ公刊の確証であり“書誌”の一部であると嘯き、オークションに現れた商品の写真を、消される前に保存して、これまた無断転用している姿勢などにも表れているかと思います。
それを公開している【明治・大正・昭和初期 詩集目録】のコーナーというのは、かつてJ-BISCと呼ばれ図書館業務で重宝された国会図書館蔵書目録のCD-ROMから、日本の近代詩集(911.56)の書誌データを抽出した一覧リストで、そこに自分の蔵書はもとより、お仲間から提供されたり、上記オークションから拾ったりした詩集の画像を、手当たり次第にリンクしていったものです。
書影だけでなく、全文をスキャンして画像公開している詩集もあり、サーバーの容量を圧迫する原因となっています。
元来、限定版の詩集はその殆どが利益とは無縁で、然る場所で然る人に然る装釘で読んでもらいたいという意図しかありません。杓子定規に公開制限をかける銅臭の強い法権の運用にはそぐわない著作物であると考えています。
画像による全文公開は、蔵書の中からこれぞという稀覯本を選んで行っていますが、いずれ国会図書館のデジタル蔵書の公開が進んだ暁には、無用のコーナーとなる予定です。
4.「サイトでのできごと」
さて、斯様に承認欲求をこじらせたサイトですが、サイトが対象としている詩人・詩集について、関係者・研究者からの照会には随時実直に対応させていただいています。
しかしながら蔵書自慢は時には仇となり、2002年、せっかく手にした立原道造の詩集を取り上げられる筆禍に遭いました。そしてその結果、古書業界では有名だったコレクター2先輩の辱知を得、彼らの常駐する「稀覯本の世界」というサイトの掲示板に誘われ、同好の人たちと交流を持つという御縁にも与りました。何が幸いするかわかりませんね。
先程お話しした、のちに私がサーバーの居候に与るそのサイトが対象としていたのは近代文学全般でしたが、稀覯本であるための条件からして、詩集はいつでもその話題の中心でした。古本道を極めつくした孤高のコレクターだった両先輩が、ツァラトゥストラよろしく古書の山から下りてきて、そこの掲示板を通じてそれぞれ研究書では知り得ない書誌上の雑学や古書情報を、夜ごと様々に垂れ給うのです。
それまで顧客情報を握ってきた古書店を抜きにして、顧客同士による自由な情報交換が始まると、掲示板は瞬く間に日本中の若年コレクターが注目するサロンに変じました。
粋狂な蔵書家先輩の発案で、古本クイズが予告なく出題され、最初の正解者には初版本を、それも何万円何十万円もする稀覯本を惜しげもなく賞品として進呈してしまうという、とんでもない企画が度々催され、かく言う私も自分の掲示板から出張してお道化まわり、本来手にすることなど叶う筈もない日夏耿之介の詩集『転身の頌』(両親に宛てたNo.2本!)をいただきました。詩人の集まりとは一風異なる蔵書家コレクターのオフ会に参加したのも忘れられない思い出です。
2先輩の話は面白い逸話でいっぱいで、ここでは措きますが、これは最初に申し上げた、牧歌的なインターネット環境で起きた恐らく最初で最後の、奇跡的なお祭り騒ぎの一年間だったので特記します。
それが開設して4年目2003年頃のことで、今だに私は当時の掲示板常連からはハンドルネームで呼ばれます。そしてこれがきっかけで私のサイトは、田中克己をはじめ昔の詩人を顕彰している文学サイトの変わり種として認知されるようになりました。
5.「江戸漢詩との出会い」
以降に検索などでサイト内のコンテンツに直接たどり着いた人の中には、あるいはここを地方の漢詩文を紹介するアーカイブのサイトとして認知して下さっている人もありましょう。
が、これもまた四季派周辺の文学者だった中村真一郎や富士川英郎を緒とする、戦後に起こった江戸漢詩再評価の道行きをなぞった結果であります。
2014年、図書館のポストから外された私は、私生活でもストレスを抱え込み、同じく精神の危機から恢復した中村真一郎に倣って、江戸時代の抒情詩すなわち漢詩に親しむことを覚え、彼らの伝記や論語の素読、漢検の受検にも没頭しました。実学志向の流れから、世の中では文学部がどんどん消滅してゆきましたが、職場の大学では書道コースだけが残ったのも幸いしました。
経済的な余裕はなくなりましたが、世の中は本離れが進み、古書が市場に余り始め、さらにネット書店やオークションの普及が相場の暴落に拍車をかけてゆきました。私が狙っていた、需要も供給も少ない近代詩の稀覯本に変化はありませんでしたが、一方で、人気復調の兆しがあるとは言え、草書・訓読・典故と敷居の高い漢詩文はまだまだ研究者の領分であり、稀覯本である筈の百年以上前の漢詩集も成金コレクターの対象外となっていました。
ですから「地域から発信」する内容を江戸時代にまで拡張し、新たな顕彰対象として漢詩人を加えたのは、詩文学の歴史における当地美濃地方の先人たちの活躍ぶりを考えたとき、田舎に帰郷した私がいずれたどり着くべき場所だったのかもしれませんが、そこに至るモチベーションには、右に挙げたいくつもの環境と条件とがあったのです。
若い頃は興味を持つことのなかった、田中克己先生の本業(東洋史学)の一端である、中国文学の世界と図らずも際会することになったのも、時間をかけて再度めぐり合った御縁だったといえるでしょう。
この方面の成果としては、なおさら地味で何の注目も集めませんが、宮田嘯臺[1747-1834]や戸田葆堂[1851-1908]といった漢詩人をはじめ、地元岐阜にまつわる文献資料の公開をしています。
最近では2016年にオークションで写本の束を入手し、その出所(小原鉄心による未刊アンソロジー)をつきとめ、各作者(大垣藩臣の河合東皐[1759-1843]と木村寛斎[1799-1843])の自筆詩稿に訓読を施した翻刻を今年ようやく了えたところです。
6.「これから」
詩を書かなくなって久しいですが、1961年生まれの私も還暦を迎え、退隠を控えて、和本を小脇に手挟んで散歩する爺むさい風姿にあこがれるようになりました。近代詩集の代わりにぼつぼつ購入してきた、版本の端本や、真贋の入り乱れた掛軸の解読に勤しんでいるこの頃です。
ただ近代詩の分野においても引き続き、各地に埋もれた資料発掘に携わっておられる方々の活動紹介に努め、サイトでは田中克己以外にも、盟友だった杉山平一、小山正孝を始め、ここでしか読むことができない、高木斐瑳雄、一戸謙三、佐藤一英など「地域からの発信」に重きをなしたマイナーポエットたちの資料を提供する場として、在野の研究者の方々との連携を大切にしてゆきたいと考えています。
田中先生の日記は今もなお翻刻の途中ですが、各御遺族から著作権(公衆送信権)の承諾をいただいて公開している電子資料は、いずれも公共機関による管理が望まれるものばかりです。
今後も公の機関が手を出しづらい、著作権が不分明な領域を補完するかたちで、その行き先が決まるまでの間、暫くこのままの形で公開を続けてゆくことになりましょう。コンテンツの存在意義について、適宜再確認しながら着地点を考えてゆきたいと思います。
多くの方々の理解と協力と黙認とを以て成り立っているこのサイト上の資料と情報とについて、関係する著作権を利己的に主張するつもりは今後も一切ありません。
コンテンツは現在、大まかに次の様な構成になっています。(アドレスshiki-cogito.net)
【田中克己文学館】 先師の詩業、日記、アルバム写真などを公開。
【明治・大正・昭和初期 詩集目録】 前述した書誌DB。所々、一次情報(本冊)を公開。「四季」「コギト」総目録を併載。
【四季派の外縁を散歩する】 と 【書評 BookReview】。戦前のマイナーポエットに関する管理人の文章。
【濃飛百峰 岐阜県の漢詩人たち】 江戸時代後期に活躍した郷土詩人の文業。
【LINK】 前述した掲示板サイトなど、とりまぜて紹介。
【管理者日録】 本サイトの掲示板と、恥ずかしい【過去ログ】
【Twitter】 現在頻繁に更新しています。(@cogito1961)
新刊書店の詩のコーナーでは目にする機会のすくない、滋味の深い戦前抒情詩と江戸漢詩の世界に是非触れてみて下さい。感想・要望・御指摘など御気軽にお聞かせいただければ幸いです。
付記【自己紹介:詩集】
『中嶋康博詩集』 2013.5.31潮流社刊, 126p ; 21cm上製・函 付録8pつき
内容 Ⅰ:夏帽子(1988)より Ⅱ:蒸気雲(1993)より Ⅲ:雲のある視野(拾遺篇) サンプルを添付しました。ご覧ください。
私は自分の詩作について、四季派の抒情詩なるものを継いで書いてきたとそれなりに自負はしてゐますが、
思ふにあまりにも自分ひとりの世界に即しすぎ、他者の気配が全くありません。
当時詩集をお送りした方々からもその指摘を受けましたが、これはこれで仕方がないことと思ってゐます。
自分の詩が時代からも孤立してをり、詩壇から評価されなかったため、その後、詩との付き合い方も自然、自作から祖述へと変っていったのですが、
これは過去の詩作を客観視できるやうになり、先師の集成詩集の装釘に倣ってまとめた一冊です。
一般書店では販売してをりません。メルカリ匿名配送にてお求めくだされば幸甚です。
Back Top